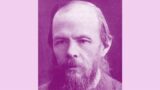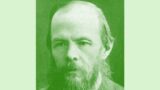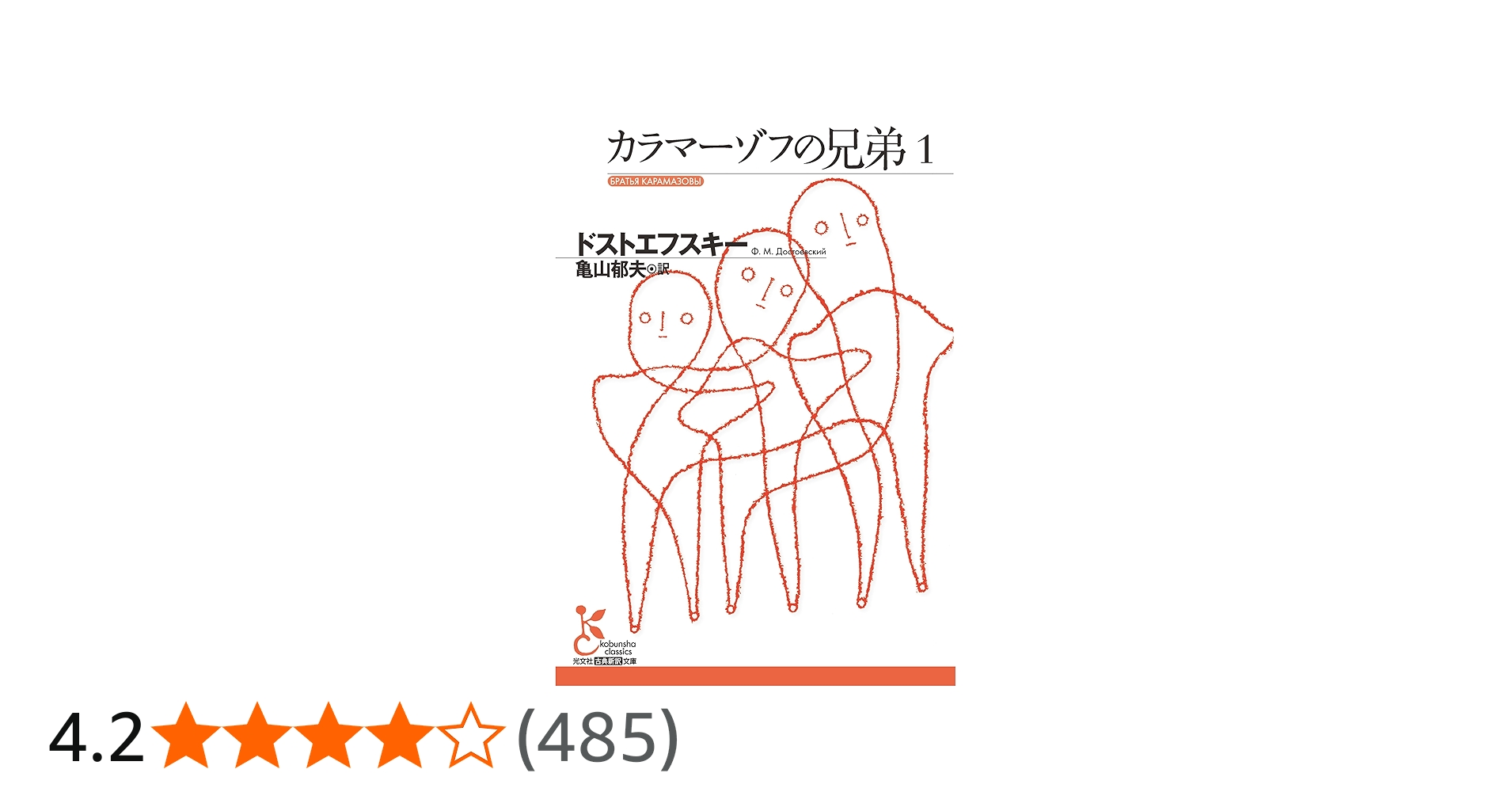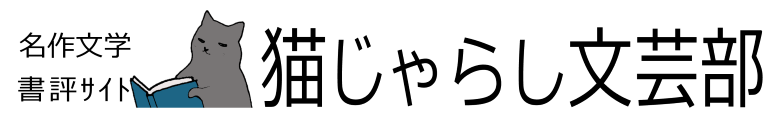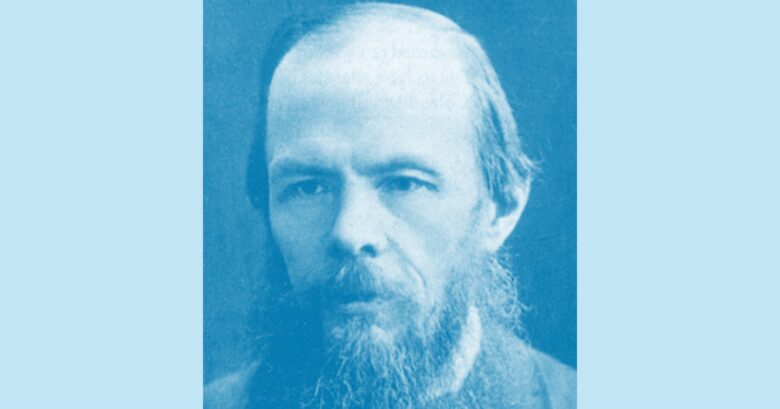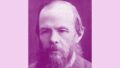『カラマーゾフの兄弟』は、宗教や哲学、思想の小説として読むことができます。
形而上学的な問いとして、神の存在と不在を考えさせられる部分が、第二部第五編の「プロとコントラ」と第六編の「ロシアの修道僧」です。
神か悪魔か、善か悪か、個人(個人主義)か全体(共同体)かという二元論で、対の関係になっています。
そこには「人間とは何か」という実存の問題があり、生きる意味や使命を問うています。
この動画では、「ロシアの修道僧」のなかの「ゾシマ長老の談話」とアリョーシャのその後について考えてみます。
★以下の動画もぜひご覧ください↓
内容は、「大審問官」で語られた、人間はパンのために、魂の自由を統治者に委ねることを選択したことに対するゾシマ長老の考えが語られています。
「大審問官」の話が、イワンの頭のなかで考えられた世界であるのと同じように、「ゾシマ長老の談話」は、アリョーシャがまとめたものとなっています。
よって、イワンの場合ほどではありませんが、アリョーシャの思いや共感するもので構成されています。
これはゾシマ長老の死後、俗界に下りたアリョーシャの血肉となる思想といっても良いと思います。
イワンのつくった「大審問官」の話は、16世紀のスペインが舞台でした。アリョーシャがまとめた「ゾシマ長老の談話」は、19世紀のロシアです。
ローマ・カトリックあるいはプロテスタントとロシア正教の違いでもあります。
ゾシマは、当時(1866年)のロシア、つまりは近代化(資本主義化)が進むなかで、神の権威が薄れつつあることを認めますが、だからこそロシアの大地から救済者が出てくることを信じていると話します。
ゾシマもまた、イワンと同じように幼児虐待を例にあげて、このような不条理は失くさねばならないと説きます。しかしヨーロッパに見られるように、力による民衆の反抗(フランス2月革命)を否定します。
怒りは、互いに殺しあうことになり、最後の二人になってもなおお互いの傲慢さから相手を殺し、ついには自分も滅びることになるだろうと説きます。
「大審問官」でテーマとなっている「自由」について、
その意味をゾシマは説きます
彼らは「自由」と言っているが、そもそも彼らの言う自由とは何なのか?と改めて確認をします。
現代は科学が中心で、神の顔や神の真理が歪められようとしている。しかし科学の中にあるものは人間の五感に属すものだけで、人間存在の高尚な半面である精神世界がしりぞけられている。
人びとは「欲求を満たすこと、、それを恐れず、むしろ欲求を増大しようとする」そのことを「自由」と捉えているようだ。
これこそが俗世における現在の「自由」の教えなのだ。
つまりは、もっと、もっと、もっと、自分の思うがままに。ということでしょう。
限りない欲望ということになります。
この欲求を増大させる権利からどんな結果が生ずるだろうか?
富める者は、孤立と精神的自殺、貧しい者は、妬(ねた)みと殺人に向かっていく。なぜか?それは「自由」を求める権利は与えられていても、その欲求を満たす手段は示されていないからである。
まさに近代がもたらした自由競争の結果としての社会の姿です。
弱肉強食や優勝劣敗の原理であり、勝者、敗者どちらにも道徳の崩壊や精神的な病を引き起こすと言っているわけです。
世界がますます一体化し、結びつきが強くなり、距離が縮まり、思想は瞬時に伝達される。これを人間同士の一体化などと信じてはいけない。
いかがでしょうか?
これはまさに現代で言うグローバリズムそのものではないでしょうか。金の力、まさに資本主義(近代化)で浸蝕していく自由主義の社会です。
このゾシマのこの指摘は、ドストエフスキーの見た西欧文明の近代化の実態、そこにある疑惑と不信です。
当時の皇帝、アレクサンドル二世の農奴解放(一八六一年)は失敗しました。農民たちは豊かになるどころか、ますます貧しくなり体制への不満が高まります。これはナロード(農民を中心とした民衆)ニキ運動へと向かっていきます。
資本主義で貧富の差が激しくなり、社会は混乱するばかりです。
彼らは、自由というものを欲求の増大とすみやかな充足と理解することで、自らの本質を歪(ゆが)めている。人間の本質はそこにはない。
無意味で愚かな願望や習慣は、ばかげた思いつきを産み落としているだけで、人々は、お互いの羨望と、色欲と、虚栄のためだけに生きている。
そのために、命や、名誉や、人間愛まで犠牲にして、その欲望を満たし、それができないとなると自殺さえしかねない。
貧しい人は、欲求不満と羨望が、酒で紛らわされ、いずれは酒の代わりに血に酔いしれるだろうことは、目に見えている。これは暴動や殺人を指していますね。
こうした人間が、はたして自由なのか? 修道僧の歩むべき道は、これとは別である。
不必要な欲求を断ちきり、傲慢な自己の意志を贖罪の労役によって鎮め、神の助けを得て、精神の自由と精神的な喜びを勝ち取るのだ。
つまりは心の奥底に神を宿しておかなければならない。
神を信じない指導者は、たとえ心が誠実で、知力が卓抜でも、ロシアでは何ごともなしえない。
民衆はそのような無神論者を倒し、統一された正教のロシアが生まれるだろう。
民衆を大切にし、民衆の心を守らなければならない。静寂のなかで民衆をはぐくみ育てることだ。これこそが修道僧の偉大な仕事である。
上からの権力の行使ではなく、神によって、民衆から湧き上がるものでなければならないというわけです。
神が宿る民衆がいて、神と民衆が結ばれる精神共同体となることが必要と説きます。
それが正教であり、ロシアの大地と結びついた信仰であるとするものです。
民衆は、真理を信じ、神を認め、感動にむせび泣く。
上流の人々は、科学の言いなりになり、キリストぬきで、自分の知性だけをたよりに正しい社会をつくろうとし、犯罪もなければ罪もないと広言している。
神を持たないものにとって、犯罪という概念は何ら意味をなさないからだ。
ロシアの民衆は、貧しくなればなるほど、身分が低くなればなるほど、彼らのなかで立派な真理が明らかになるのだ。
貧しき人々のなかにこそ神が宿っており、金持ちの富農や搾取者たちは、大半が堕落している。
大地にひれ伏し、大地に口づけをしなさい。
すべての人々を愛しなさい。
熱狂を恥じずに、尊ぶがよい。それこそ神の偉大なる贈り物であり、
選ばれた者にのみ与えられるものだから。
ゾシマは、アリョーシャにも
『一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただの一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる』(『ヨハネによる福音書』第12章24節)
と説きます。
ロシアの大地に命を捧げること。民衆(ナロード)を愛し、救うこと。それこそが、俗世界へ出ていくアリョーシャの使命となっているのです。
ここに、身を捨てて尽くすことの必要さを説き、アリョーシャの思いは燃えることになるのです。
イワンとアリョーシャの違いは何か?
「大審問官」の物語詩で明らかになったイワンの無神論の立場とは逆に、アリョーシャはキリストとともにある、ところから始まっています。
アリョーシャは、すべてにおいて、キリストの存在が前提となっているのです。ここがイワンの無神論とは正反対なのです。
ただしイワンから聞いた幼児虐待の話には、極刑あるいは私刑を望む発言をしています。アリョーシャの心のなかにも非道な行為に対して強い復讐心が宿っているのです。
ここからが第二の小説に表されることだったのでしょう。
アリョーシャは、作者ドストエフスキーが「私の主人公」と評したように物語の中心人物とされています。
さらに“著者より”という<序文>に、この長編をふたつからなるものとし、「第一の小説」が『カラマーゾフの兄弟』であり、「第二の小説」の方が重要であるとしています。
しかし「第一の小説」である『カラマーゾフの兄弟』を発表後、二か月して、ドストエフスキーは亡くなってしまい、第二の小説は未完となりました。
推測ですが、きっと、修道院から俗なる世界に出て、現実を知るなかで、アリョーシャの精神は少しずつ変化していくのでしょう。
その基盤にはゾシマ長老の教え、キリストがあるのです。
アリョーシャは修道僧の世界に身を投じた理由は、信仰心は奇跡から生まれるのではなく、奇跡が信仰心から生まれる。
つまり信仰心を極めることで奇跡が起こるという順序です。
イワンは、神の存在を信じながらも、不条理な現実世界のなかで、引き裂かれた末の無神論者です。
そして合理主義のもとで選民的なエリートが、社会を治めるべきと考えています。
大審問官と同じように、人間を諦めており、憂いをこめながらも、強い意志を持って人間を力で管理しなければならないと考えているようです。
そんなイワンは、後の物語の展開では、合理主義の内心に潜んでいた父殺しや遺産相続に対しての自身の本心に対して、苦悩した挙句に、精神を病んでいきます。
これに対して、アリョーシャはどうなっていくのでしょうか?
アリョーシャはゾシマ長老の愛弟子という関係ですが、そのゾシマが死んでしまいます。高僧の亡骸は腐らないとの言い伝えがあるなかで、アリョーシャはゾシマの遺体から発する腐臭に衝撃を受けます。
動揺し信仰が揺らぎ始めるアリョーシャですが、夢のなかで「自分の仕事をはじめなさい」というゾシマの声を聞きます。
大地に倒れ込み泣きながら口づけをして、大地を永遠に愛すると誓います。こうしてアリョーシャの心のなかに意志が確立されるのです。
ここが、まさにドストエフスキーが唱える「土壌主義」です。
アリョーシャは。大地と一体になることを知るのです。
アリョーシャは合理的ではなく、直感的なのです。そしてキリスト的な社会主義者として思想的な基盤を持ち始めるのではないかと思われます。
だからドストエフスキーは、「アリョーシャは修道院から出て革命家にしようと思っていた」と語っているのだと思います。
では、「大審問官」の行為と何が違うのか?それはイワンの支持する統治のかたちは権力者による専制政治です。
イワンの苦悩。神の存在は信じる。しかしこの世界は神が創ったものではない、という考え方は、ある意味では自己矛盾に陥っている状態です。
論理的な思考が邪魔をしていといえるかもしれません。
「神がいなければすべては許される」と、自分に言い聞かせながらも、罪の意識との狭間で精神が壊れていくのです。
どうやらアリョーシャはそのようには考えないと思われます。何故か?
その理由は、アリョーシャは奇跡は信仰心から生まれると考えおり、自分がキリスト的な社会主義者だと信じているからです。
イワンは自分が悪魔と手を結んでいると苦しみますが、アリョーシャはキリストの教えによって悪魔をしりぞけようと考えています。
物語の第四部に登場した、自らを「ぼくは社会主義者です」というコーリャという少年がアリョーシャに向って言うセリフ。
「キリスト教の信仰が奉仕してきたのは、金持ちと有名人だけじゃないですか。下層階級を奴隷状態に押さえつけておくためです。」
コーリャは、その一方で、こうも主張します。
「ぼくはキリストに反対しているわけじゃないんですからね。キリストはほんとうにヒューマンな人ですし、ぼくらの時代に生きていたら、すぐにでも革命家の仲間に入って、きっとめざましい役割を果たしたでしょうね」
これはペトラシェフスキーの会のメンバーだったドストエフスキーが思想家ベリンスキーの口から直接、耳にした言葉から生まれたセリフとされています。
アリョーシャはコーリヤに向かって「きみは不幸になる」と言うと、コーリヤは「わかっています」と答える。予言するような言葉に対して、どこかコーリャの使命感すら感じる。
未完となった第二の小説は、第一の小説『カラマーゾフの兄弟』から一三年後(一八八〇年)が描(えが)かれたとされます。
続編では、三三歳になったアリョーシャと二七歳になったコーリャと、かつての子供たちと共に、テロルを企てることが大きなテーマとなるのでしょうか。
コーリヤが実行犯(ペトラシェフスキー事件)で、その後のドストエフスキーが聖書のなかにキリストの生き方を敬ったように、アリョーシャはその後のコーリャの精神的・思想的な支えとなるのかもしれません。
こうして、いよいよ前夜と言う意味で、第一の小説の最後のエピローグ、アリョーシャの素晴らしい演説の後で、子供たちが声を合わせて叫びます。
「カラマーゾフ万歳!」つまりは「革命万歳!」という意味ではないでしょうか。
コーリヤをはじめとした一二人の子供たち(使徒)によって、暗示的に、アリョーシャ(キリスト)は師として讃えられているようです。
ロシアを救うのは、かつて抱いた空想的(ユートピア)な社会主義ではなく、キリストの教えを基盤とした民衆と共に確立する社会主義ということでしょうか。
最後にドストエフスキー亡き後のロシアの駆け足の歴史と現在を考えてみます。
アレキサンドル二世が革命グループ「人民の意志」によって暗殺(一八八一年)され、この三六年後、ついにロシア革命(一九一七年)が起こります。
中心となるレーニンは無神論者です。正教会を弾圧し、教会も取り壊します。そしてスターリンの恐怖政治となっていきます。
人民が苦しむ暗黒の共産主義のなか第二次世界大戦が終わり、以降の冷戦の時代を経てソ連は崩壊(一九九一年)します。
歴史はさらにさらに進んで、ゴルバチョフのペレストロイカを経てエリツィンの時代ではアメリカ主導の自由主義に翻弄されます。
そして二〇〇〇年に就任したプーチンは、統治理念としてロシア正教を中心に置きます。
教会を増やし、大地(ロシア民族の信仰や文化や歴史)にかえろうとしました。
プーチンは、「ドストエフスキーは天才的な思想家だ」と作家の生誕二〇〇年の際にドストエフスキー博物館でノートに記しています。
現在のロシアの統治者としてプーチンは、ロシア正教会を大切(プーチンも洗礼を受けている)にしながら、ユーラシア(ヨーロッパ+アジア)に君臨する強国を建設しています。
イワンの思い描いた「大審問官」のように、人間へのパンを保証することで強い統治を行うという現実の側面と、アリョーシャのまとめたゾシマの「談話」のようにロシア正教を支持し民衆と共に統一したロシアを建設するという理想の融合のようにも見えます。
その意味では、プーチンはドストエフスキーに学ぶ部分があるのです。そしてドストエフスキーの思いもまた、いくらかは叶えられたのかもしれません。
「自分はすべての人に対して罪がある」だから「傲慢を捨てよ」
魂の救いとは何か?人間の精神を深く揺さぶる、この最高傑作は、人類が生き続ける限り神の存在か非存在かという原初に立ち返りながら、信仰と理性、自由と服従、個人と国家という実存の意味を問い続けることでしょう。