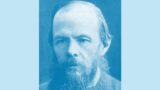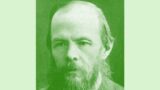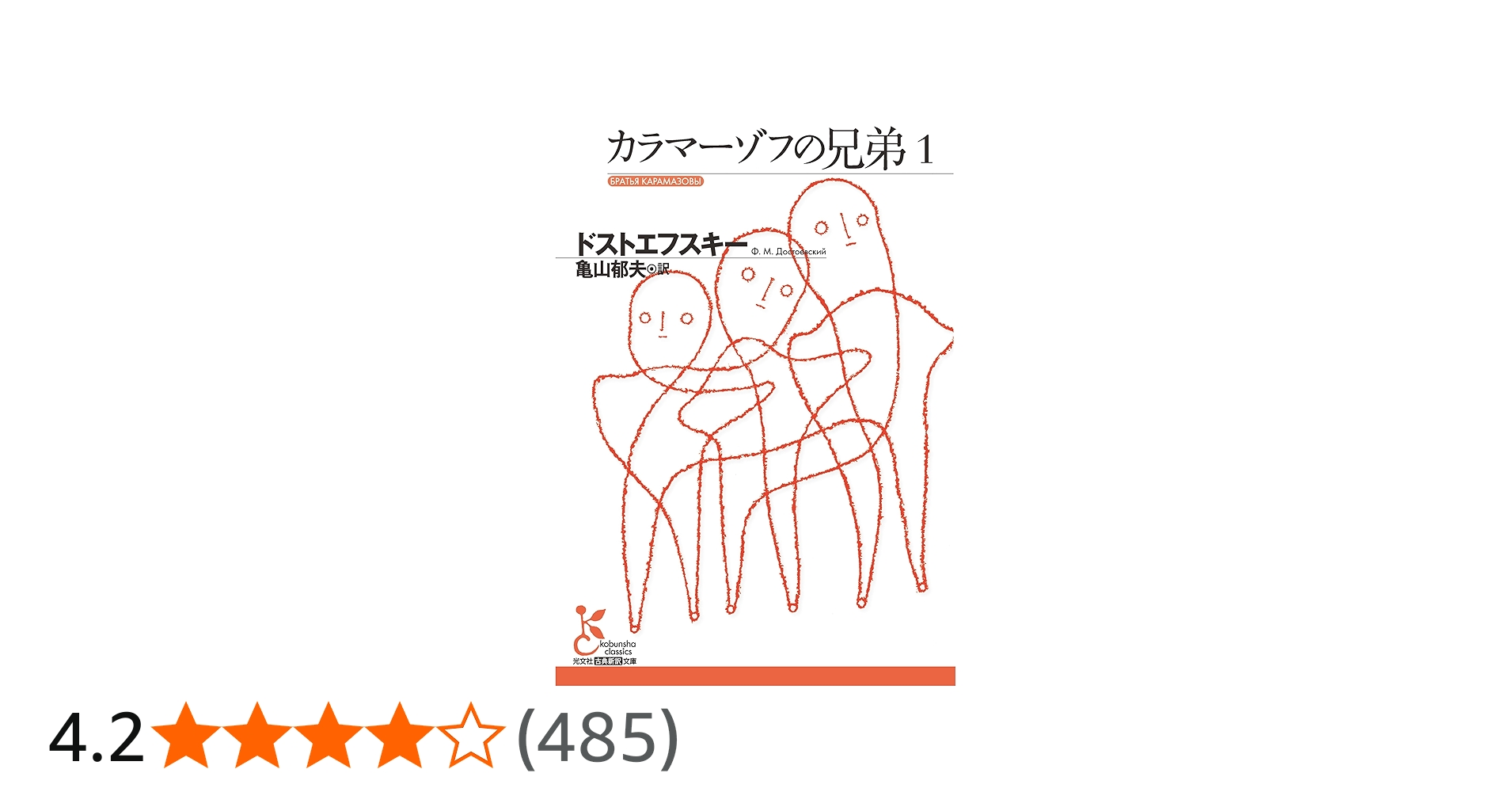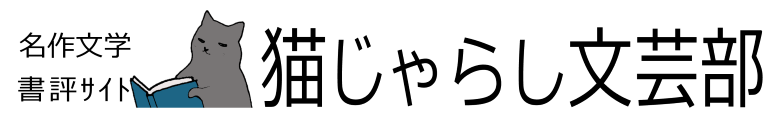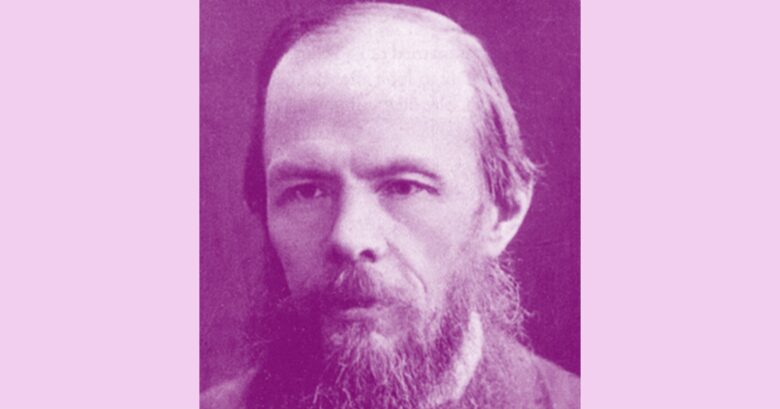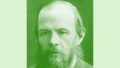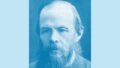『カラマーゾフの兄弟』は、宗教や哲学、思想の小説として読むことができます。
形而上学的な問いとして、神の存在と不在を考えさせられる部分が、第二部第五編の「プロとコントラ」と第六編の「ロシアの修道僧」です。
神か悪魔か、善か悪か、個人(個人主義)か全体(共同体)かという二元論で、対の関係になっています。
そこには「人間とは何か」という実存の問題があり、生きる意味や使命を問うています。
この動画では、「プロ(肯定)とコントラ(否定)」のなかの有名な『大審問官』とイワンのその後について考えてみます。
★以下の動画もぜひご覧ください↓
作品の舞台となる一八六〇年代のロシアは近代化のなかにあります。
人々は、神への信仰が揺らぎ、新たな神となったのは、金です。まさに金を信仰します。
人間の本質が問われるなかで、人々は自由をはき違え金に執着する強欲な拝金主義者となっていきます。
こんな時代だからこそ、ドストエフスキーは精神の問題を避けて通れなかったのでしょう。
「人はパンのみに生きるにあらず」という福音書の言葉をめぐり、自由か、パンかの議論となり、次男イワンと三男アリョーシャの神学的な論争となります。
無神論のイワンと神を信じるアリョーシャの対話です。
「神は存在するのか、しないのか」
このことは、ドストエフスキーの内なる葛藤でもあります。
カラマーゾフの三兄弟の一人、イワン(次男)はモスクワの大学を出たインテリです。神の権威の失墜と資本主義がもたらす唯物的な社会、つまり近代への問題意識が強く背景に現れています。
イワンは、アリョーシャ(三男)に、はっきりと「自分は神の存在を信じている」と前置きします。しかし、「神が創造したとされるこの世界」を否定します。
イワンの心のなかでは神はいるのでしょう、しかし現実世界では神はいないのです。これは合理的な思考をするイワンのなかで、矛盾となっています。
どういうことでしょうか?
イワンはこの世界で今日も起こっている子供たちへの虐殺、虐待、人身売買の事実をアリョーシャに話します。
何の罪もない赤子がむごたらしく殺され、少年が捨てられ、少女が折檻を受ける。
イワンの目から見れば、その行為は人間ではなく悪魔の所業です。
当時は、ロシアを始めたくさんの幼児虐待の事件がありました。
イワンは、アリョーシャに問いかけます。
ある農奴の少年が地主の犬を傷つけてしまったため、地主はその少年を、母親の見ている前で裸にして、猟犬の群れをけしかけてかみ殺させた。
「さぁどうだ・・・この地主を道義心にてらして銃殺にすべきか、言ってみろ」と、イワンはアリョーシャに迫ります。
アリョーシャが、蒼白く歪んだ笑いを浮かべて「銃殺です!」と答えると、イワンは「でかしたぞ!」と感激して叫ぶ。
神は人間による報復を禁止しています。だからイワンはしたり顔で、「りっぱな修道僧さんよ、お前の心のなかにも小さな悪魔がひそんでいるってわけだ」と言います。
イワンはアリョーシャの信仰ではなく本心を求めているのです。現実(心のなかに棲む悪魔)をもっと直視しろと言っているのかもしれません。
「神さまはいったいどこにいるんだ」「神さまは何故、でてこないんだ」
「神さまがいるなら、なぜ純粋無垢な子供たちの虐待を見過ごしているのか」
加害者を許し、天国で再会し、大調和をするのか。「汝、隣人を愛せ」と言われてもできない。たとえ、母親たちが、死んだ子供たちが、迫害者を許したとしても、俺は絶対に、許すことはできない。
俺は人類を愛している。しかし、そこまではできない。俺は決して神を受け入れないわけではないけれど、それはできないことなんだ。
イワンにとって、キリストの戒律そのままに、他の人間を自分自身と同じように
愛すること―それは不可能なのです。これはニヒリストの視点です。
アリョーシャは「それは反逆ですよ」と小声でつぶやき、すべてのことに対して、ありとあらゆるものに対して赦(ゆる)すことのできた人、あらゆるもののために罪なき自己の血を捧げた人、キリストがいたからこそ、未来の調和が建設されるんですと説きます。
すると、イワンはせっかくの機会だから自分が創作した物語を聞いてくれと言います
ここからが「大審問官」の話です。
これはイワンが作った叙事詩です。イワンの創作なのです、現実ではありません。苦悩の果てに無神論に辿り着いたイワンの心情の吐露なのです。
舞台は十六世紀のスペイン、セヴィリアの町。そこでは毎日のように異端審問(宗教裁判)が行われ、邪な異教徒が火炙りの刑に処せられています。
昨日も、百人の異端者が枢機卿(高位聖職者)である大審問官の手で焼き殺されたばかりでした。
人びとは信仰と熱情のなかでキリストの再臨を待ち望んでいます。
スペインの黄金時代、皇帝権力という専制の時代です。それは異端派への激しい弾圧によって成り立っています。そこに、人知れず一人の男が姿を現します。
男が、人々の手に触れると、次々に病が治っていく。子どもの頃から盲いの老人の目を開いたり、死んだ幼い子供が生きかえるのです。 群衆は、動揺し、どよめき、慟哭します。
男の正体はすぐに気づかれました。民衆は男に殺到し、取り巻き、後をついて歩きだします。
九〇歳の大審問官は、この男のことを知っています。あの男でなければ、こんな奇跡を起こせるはずなどないからです。その者を召し捕れと命じます。大審問官の権威は絶大なので、民衆は皆、ひれ伏します。
老いた審問官はこの男を牢に閉じ込め、闇のなかで対峙します。
「お前はキリストなのか?キリストだろう?」
「なぜ、われわれの邪魔をしに来た?」
「明日には、おまえを最悪の異端者として火炙りにしてやる」というのです。
この「邪魔をしに来た」という意味は、キリスト教をローマ教皇に委ねたのに、一五〇〇年もたった今、人間の世界に降りてきて奇跡をふりまくからです。この奇跡が今さらに邪魔なのです。
どういうことなのでしょう?
大審問官は九〇年間、黙りつづけたことを語り始めます。その内容は、何とキリストを罪人として糾弾をするものでした。
聖書のなかで、悪魔がイエスに言ったとされる「砂漠の誘惑」とされる三つの問い(マタイの福音書4章)があらわされます。
ひとつ目
悪魔はイエスに言います「石をパンに変えてみろ。そうすれば人類はお前に従うだろう」
物質的な豊かさによって人々は救われるということですが、イエスは「人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる」と答え否定します。
パンによる服従ではなく、人間の自由な意志を望んだのです。
しかし、結果は、パンの争奪となり戦争が絶えない。自由な意志で天上の理想を求めることを期待しても、人間はそんなに強くなく、まず食を求め苦しんでいることをお前は分かっていなかった。
彼らは自由を差し出して、いっそ奴隷にしてください、でも食べ物は与えてくださいと言うだろう。
ふたつ目
悪魔はイエスに言います「神殿の屋根の端に立たせて、そこから飛び降りてみよ、神の子ならば天使たちが助けてくれるだろう」
そのことによって神への信仰が証明され、人々の信頼を獲得できるというものですが、イエスは「あなたの神である主を試してはならない」といって拒否します。奇跡による信仰ではなく、自由な信仰を望んだのでした。
しかし人間というものは奇跡を求めている。自由な精神から信仰が生まれるのではなく、奇跡から信仰が生まれるのだと悪魔は言います。
みっつ目
悪魔はイエスに言います「もしひれ伏してわたしを拝むなら、地上の王国と栄華を与えよう」
するとイエスは「退け、サタン「『あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ』」と言って拒否します。こうして、悪魔から人間の自由を守ります。イエスは人間の自由を奪うことをしませんでした。
大審問官は言います。
お前は「自由」というが、人間は自由などという重荷に堪えられる存在ではない。
彼らは自由とひきかえにパンを与えてくれる相手を探し、その前にひれ伏すことを望んでいるのだ。
われわれはかれらを自由の重荷から解放し、パンを与えてやった。そうしないと神の真実にも異議を唱え、神の王国を崩壊させかねないからだ。
大審問官は、奇跡、神秘、権威の三つの力が、人間たちを幸せにし、反逆者を打ち負かし、虜にすることができる。と言います
それなのに、お前は奴隷的な信仰ではなく、人間に自由な意志と愛を望んだ。
そこを救ってやったのがローマ・カトリック教会であり、教皇以下の特権階級だというのです。
人間の自由を取り除くことで、彼らの心に安らぎを与える。服従できることが幸せだと彼らは悟り、われわれに従う。彼らの罪は我々、一部の受難者が引き受ける。
人間は天国にはいけないが地上での幸福は享受することができる。 アリョーシャは、それはカトリックの権力欲だと言って、イワンを諫めます。
この「自由」とは解釈が難しい面があります。どう捉えるべきでしょうか?
私は、「自由」とは何者からも命じられず、強制されず、隷属することなく、自らの意志に基づき生きることができる状況だと思うのです。
ただし、そのためには、精神の自由が必要なのだと思います。それには自分自身で善く生きる意味や使命とは何かを考え実践しなければなりません。
自分を律しながら生きるって、なかなかたいへんなことですよね。この場合は規範としてのキリストの教えがあり、神への祈りと愛ということなのでしょう。
しかし大審問官の考えは、
人間は、ほんとうは精神の自由など求めてはいない。「自由(天上のパン)よりも地上のパンを求めて」反逆をしているのではないか。つまりは物欲しかないということです。
「だから人間に自由を与えたおまえこそが最大の犯罪者だ」として大審問官は糾弾し、二度と人間の世界に現れないように、再び現れれば、異端者として火炙りの刑に処すと告げます。
最後に、大審問官は「われわれは、もうだいぶまえからおまえにつかず、あれについている」と言います。
このおまえとはキリストのことで、あれとは悪魔のことです。
われわれはキリストの教えに逆らっており、悪魔の側についていると明言しているのです。
男(=キリスト)は黙って大審問官の話を最後まで聞き、何も言葉を発しない。そして別れ際に大審問官にキスをします。
大審問官は動揺しながら、「さあ、出ていけ、もう二度と来るなよ・・・絶対にくるな、ぜったいに!」と言い放ち、イエスを解放します。
繰り返しますが、これはイワンの作った物語なのです。現実の話ではありません。
「で、老人は?」とアリョーシャが聞く。
するとイワンは「キスの余韻が心に熱く燃えるが、今までの信念を変えることはない」と告げます。
「じゃ、兄さんも老人と同じなんですね」とアリョーシャは悲しげに叫び、イワンは笑いだす。
知的で理性的なイワンは、幼児虐待の現実から、この世界は神が創ったものではないと、絶望のなかで無神論に辿り着きます。
この現実世界に神がいないからこそ悪魔の所業がまかり通るのです。
異端に、邪教に、犯罪に対して死の罰を与えるのは大審問官、つまりは人間です。
逆説的に言えば、人間は神に見捨てられてしまったのです。神をつくったのが、人間の想像力とするならば、現実として、その神に人間は見捨てられたわけです。
イワンはキリストよりも専制を、善よりも悪を、自由よりもパンを、という現実を直視せざるをえないと考えているのです。
人間は形而上の理想だけでは生きていけない。それはそうでしょう。
異端(邪な反逆者)ばかりが多くなる現実に対して、今さら、人間たちに「奇跡と神秘と権威」を見せられても、どうにもならないというわけです。
人間は弱く、卑しく、反逆者であり、ほとんどすべてがパンを求めている。
そのために大審問官は、強固な統治機構(教会)のなかで自由を支配し、隷属させ、パンを与える役割を実践している。
そして自由(天上のパン)という精神的な責任は、ほんの僅かな人間が引き受けていると言っているのです。
選民と凡人、天上のパンを食むひと握りの聖職者や高貴な人々と、地上のパンを食むほとんどすべての人々。
しかしこれはまさに特権階級のエリート主義とも言えます。
キリストがいなくなった世界を管理している大審問官は苦しみや悲しみすら湛えています。
九十歳の老人(大審問官)は自分たち(教会)の正当性を語ったのです。
それでは男(=キリスト)の大審問官へのキスの意味は何か?
この話がイワンの創作である以上、イワンは大審問官の行為を賛同し支持しています。
同時にキリストもまた大審問官の心中を察しているのでしょう。その意味では、現実を知りキリストの教えの敗北を認めたことでもあります。
大審問官はキスの余韻が心に熱く燃えていました。そこにはキリストの愛を感じています。しかしどうしようもない現実世界なのです。
イワンも神を否定してはいません。しかし、キリストの正しさを信じていながらも、現実の政治のためには大審問官の統治の方法を支持しているのです。
その意味では、キスの意味は「赦し」という愛もあるのかもしれません。
信仰と懐疑、この繰り返しのなかでイワンの精神は分裂していきます。これは作者ドストエフスキーが生涯、信じ疑い、悩み苦しんだことでもありました。
キリストの存在が罪だと考えたくなるほど、心が苦しめられているイワンの異常な精神が、この「大審問官」の物語にあります。
そして「神がいなければすべては許される」という考えに自分を導きます。これは、イワンの精神がカラマーゾフの下劣な悪に向かう力なのです。
権威としての教会(あるいは国家)という組織があり、秩序のために異端審問(裁判)が行われます。
つまり民衆から自由を委託され、代わりに管理をして、パンを授ける統治をおこなっているわけです。
しかし、その向かう先には、支配者たる人間が冒す過ちも看過されることになります。このことはキリスト教の敗北を意味します。
話が終ると、アリョーシャがイワンにキスをします。これもまた意味深な場面です。
アリョーシャのキスの意味は何か?
アリョーシャは、神への冒涜となるこの物語詩を作ったイワンの傲慢さに対して、弟としての心配かもしれません。その意味での愛かもしれません。
イワンは、『罪と罰』のラスコーリニコフと同じです。無神論者であり、それが社会主義、ひいてはスターリンのような共産主義という名の暗黒の全体主義に転落する危機を孕んでいます。
この先の物語では、イワンは幻覚症を病みはじめ悪魔と対話し、次第に精神に分裂をきたしていきます。
ついに、下男の私生児スメルジャコフがイワンの命をうけたとして父フョードルを殺害してしまいます。
イワンは、当初、スメルジャコフの話す意味が分かりませんでしたが、次第に、自分がスメルジャコフをそそのかしたのだと自覚し、やがて気が狂ってしまいます。
二人は分身(双生児)の関係になっています。
キリスト教徒の少ない日本では、深い理解はできません。
しかし精神の自由という概念は、仏教の教えでも良いし、宗教だけでなく哲学から学ぶことも可能なはずです。
自由とは何か?魂の救いとは何か?欲望のみのまやかしの自由を追及するだけの現代、
もう一度、深く考えなければならないテーマだと思います。
神がいなければすべて許される、ほんとうにそれでいいのか。
道徳も倫理もどうでもよくて、法律さえ犯さなければなにをしてもいいのか?
その意味では、ますます現代において考えさせられる不変のテーマだと思います。