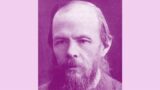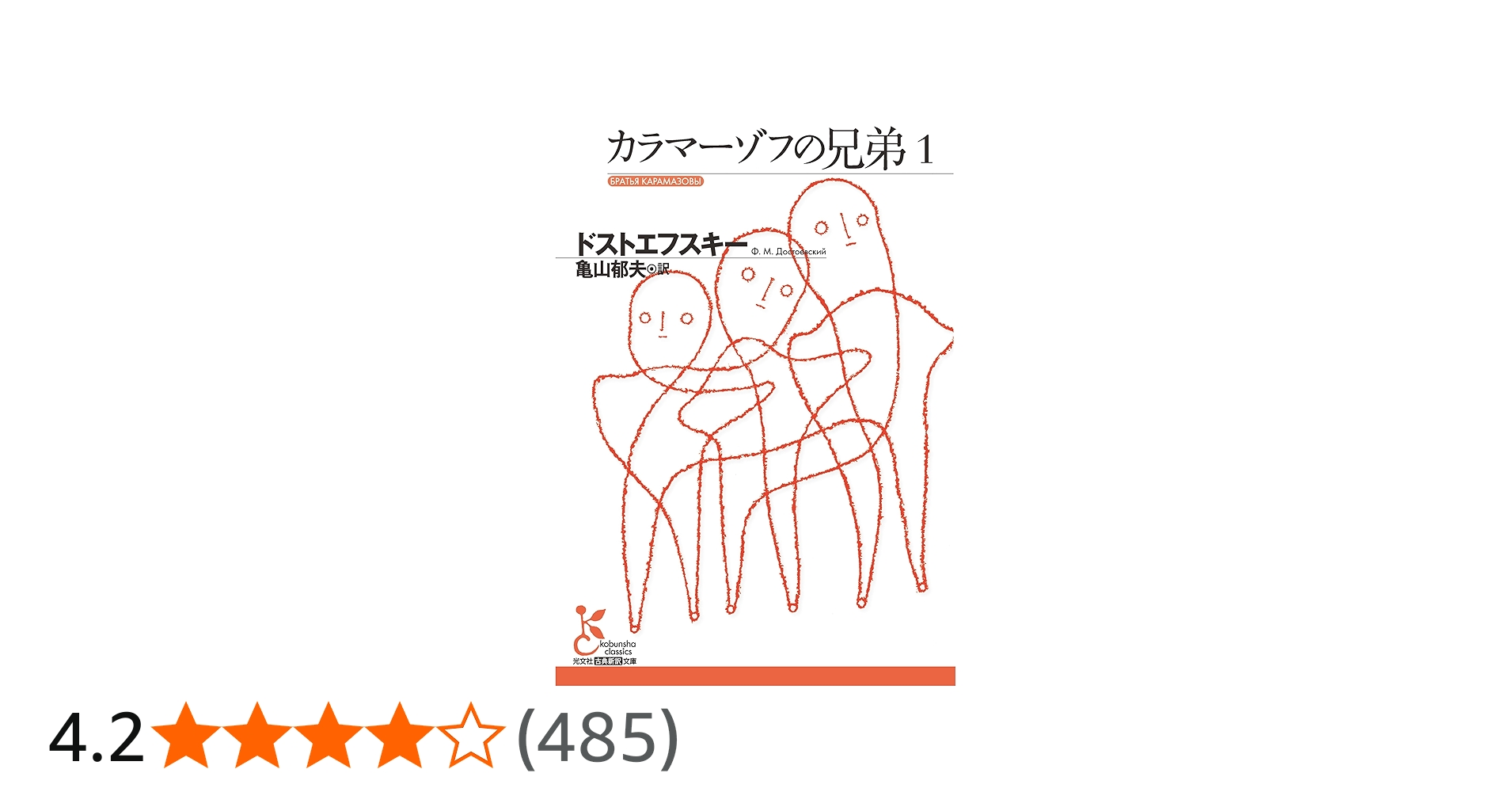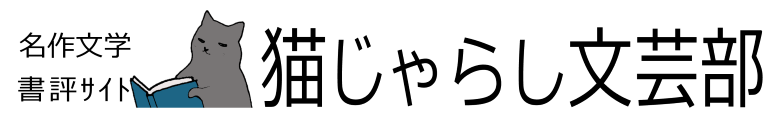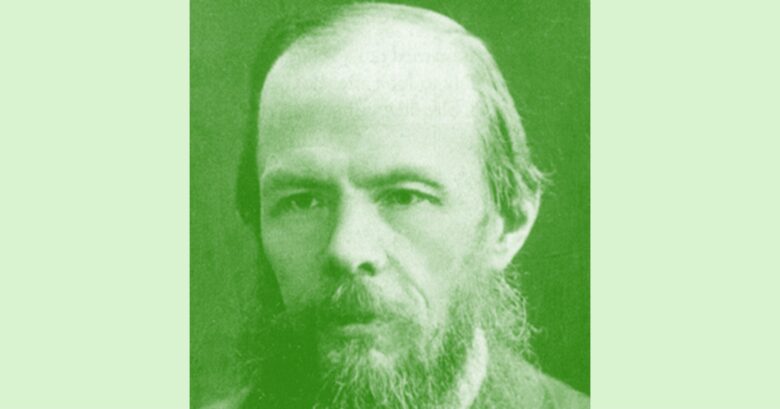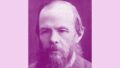この物語は「父殺し」がテーマのミステリーです。
物欲の権化で、女好きで、酒飲み、そんなカラマーゾフ家の主である父フョードル。この剥き出しの実存は、悪そのものとしての象徴です。三人の息子たち、長男ドミートリー、次男イワン、三男アリョーシャ。彼らもまたそれぞれにカラマーゾフの血を受け継いでいる。
ある夜、フョードルは何者かに殺され、傍に置いてあった三千ルーブルもなくなっていた。いったい誰がフョードルを殺したのか。
重要な脇役たち。
長男の許嫁、知的な美人カテリーナ。この女性に次男が恋心を抱く。長男と父親の心を惑わす妖艶な美人グルーシェンカ、父子でのひとりの女性の争奪戦。三角関係ならぬ五人の複雑な恋愛模様が繰り広げられます。
三男が慕う修道院の長老ゾシマ、さらには、カラマーゾフ家の料理人でフョードルが生ませた私生児と噂される、料理人の下男スメルジャコフ。
多彩な登場人物たちのなかで遺産の相続問題や恋の鞘当ての人間ドラマが進んでいく。
★以下の動画もぜひご覧ください↓
舞台は一八六六年の農奴解放後のロシア。神への祈りは薄れ、かわりに人々は金を崇拝する。時代は金が支配する資本主義に向かっています。
神の存在と不在、人間の魂を救うものは何か。
フョードルは一代で成り上がった田舎地主で、息子たちに財産を残すつもりなどなく、天国など信じず、俗世を楽しむだけの悪人として描かれます。
子どもへの愛情よりも、いつ息子に金を奪われるのかと心配し、はたまた殺されるのではないかとの被害妄想すらもっています。 激しい生への執着、剥き出しの利己心、これが当時のロシアの姿です。
一五〇年前の小説ですが、まさに中世から近代へ、神への信仰から、金への信仰へと移り変わる時代で、現代の感覚で読み進んでも全く違和感がありません。
父親フョードルに対して、長男ドミートリーは憎み、次男イワンは嫌悪し、三男アリョーシャはゾシマ長老をもう一人の父として慕う。
ドストエフスキー自身の性質が、三人の兄弟に投影され、それぞれの性格が交差し絡み合いながら高みへ上っていく。
作者最後の作品であり、自伝的要素がふんだんに盛り込まれ、生涯のテーマであった「神か革命か」の苦悩がこめられています。
この人間の精神の深みをあますところなく表現する手法として語られるのが、
ポリフォニーとカーニバルです。
日本語では多声的(ポリフォニー)、祝祭的(カーニバル)と訳されます。
ドストスキーより少し後の哲学者であるミハイル・バフチンは『ドストエフスキーの詩学』のなかで、彼の文学をそう論じました。
ポリフォニー(英: polyphony)とは何か?
音楽の世界で、ポリフォニー(多声音楽)を味わってみます。
例えば教会音楽の聖歌はそれぞれが独立した旋律をもって進みます。 これを聴くと、どこか大きな世界観を感じることができます。
それでは音楽ではなく、人間の日常を考えてみます。
私たちは、常に“違う誰か”と対話をしながら自身のアイデンティを形成しています。
“違う誰か”とは自分以外の人間が相手となることは当然ですが、自問自答という言葉があるように相手が自分自身の場合もあります。
このとき、別の人間であれ、もうひとりの自分であれ、その相手は、独立した別人格の存在なはずです。
文学上のポリフォニーの意味は、作者の視点を離れ、登場人物それぞれの自立した声や意識(自由意志)が、独自性を持ち自己主張している状態です。
その対話の対象は、相手だけでなく、自分も含まれています。人間の心や行動は時々に変化し流動的です、これを文学のなかで表現している訳です。
読了後には、とてつもなく広く深い人間の精神のドラマを感じることができるわけです。
この作品は、ドストエフスキーの自伝的な要素の集大成となっています。
そのテーマが「父殺し」。この父とは“悪”なるものの象徴です。
この「父殺し」を無意識下に願望しているのは、なんと作者ドストエフスキー自身なのです。そこで、この「父殺し」を行うために、ドストエフスキーの性質が、三人の兄弟に振り分けられます。
三人は、それぞれに自立して発言し、互いに触発しあう。それぞれにカラマーゾフの血を受け継ぎ、悩み、苦しみ、目覚めていく。
ここに三つの独立した声や意識が重なる、ポリフォニーの構造があります。
さらに脇役たちもまた、それぞれに独立した声を放ちながら行動する。
結果的に、幾層にも連なるポリフォニーの構造となっている。四部一二編+エピローグが交響曲のように深く豊かで多彩に響き渡っている。
これが最高傑作と言われる理由のひとつだと思います。
私の解釈では、人間とは、常に自身の多面的な性質と向き合い対話しており、そのことにおいて刻々と変化する存在だと思います。
俺は、昔からいっさい変わらぬ信念を持っているという人もいるかもしれませんが、私は、人間は過去の自分とは変わっていく場合も多いと思います。その方が、人間らしくもありますし、後悔や喜び含めて生きる意味もあると思います。
個人の人生は、対人関係やコミュニティや、国家や世界と繋がり、経験の質や量による変化に無関係ではいられないからです。もちろん人間だけではなく、文学や思想や哲学をはじめ、多くの体験が影響しています。
語りの多い作品ですが、このことを前提とすれば、人間の心理変容を楽しみながら、読後感として人間の深みを味わうことになります。
このことをもう少しドストエフスキーの人生に寄せて、三兄弟に振り分けてみますと・・・
ドストエフスキーの賭博好きなことはつとに知られています。稀代のギャンブル好きでありながら、人類史上最高の作品を生み出した作家ということになります。
ビギナーズラックもあったが、たいがい大負けしている。すると借金苦となる。そのために生活費の前借をして作品を書かねばならないこともあった。
悪辣な出版社との契約で執筆した『罪と罰』のときがそうだった。無慈悲でがめつい金貸し老婆が物語に出てくるのもどこか意味深だし、二本の執筆条件だったので、この後、すぐに『賭博者』という作品を書き上げた。
ギャンブルをやめることができない。では守銭奴なのか、いやそれは違うだろう。一攫千金を狙っているのか、勝ち負けのスリルが刺激的なのか、それとも逆説的に金を否定しているのか・・・、
ドストエフスキーの博打熱と浪費癖について、精神分析学者のフロイトは、父の死と共に起こった癲癇の症状に似たエクスタシーと罪悪の意識が影響しているのではともいった。
真意はドストエフスキー自身しかわからない、いや本人も正確な答えはもたないかもしれない。
尚、このギャンブルすらも皇帝暗殺未遂という過去(当局の監視)を背負いながら執筆活動をするために体制への目くらましの演技という説もある。
そう考えれば、人間の本心とは他人にはそう容易く理解できるものではない。
物語においては、この部分は、長男ドミートリーに投影されている。豪放磊落で情熱的で高潔である、卑怯者ではあるが泥棒ではない、僅かな金しか持たないかと思えば、大金を得て散財している。きっと金には淡白なのだろうと思う。
ドミートリーはいつも金にかかわっている。ドストエフスキーの金銭感覚が3000ルーブルの紛失や1500ルーブルを2回に分けるアイデアや、卑怯者と泥棒の 感覚の違いなどミステリーの謎ときとして貢献している。
さらに女性も自分の意志の赴くままに愛する。だから淑女タイプのカテリーナではなく、奔放なグルーシェンカを選ぶ。
一方で、ドストエフスキーは二七歳のとき、思想家ペトラシェフスキーが主宰するユートピア的な空想社会主義運動に参加する。
当時のロシアの貧しき人々を憂い、平等な理想の国家建設を思う。
これが皇帝(ニコライ一世)への反逆の罪として死刑判決を受ける。しかし銃殺刑直前で恩赦を受け、シベリア流刑となり五年間服役する。
この恩赦は予定されており茶番だったとされているが、だとしても銃を向けられ死を覚悟し、その瞬間に、伝令により、生に解放されるという気持ちは、絶対に当事者以外にわからない。
この一連の流れは、ドストエフスキーに、皇帝権力への反抗や革命運動、さらには死への恐怖と生の帰還いう強い衝撃を与えたことだろう。
この社会主義に向かおうとした性質は、物語においては、知性派の次男イワンの無神論のニヒリズムに投影されているとみてよいと思う。
表向きは知的なインテリで大学も自力でバイトをして卒業するが、内心では、父殺しと遺産の分け前を狙っている。
ドストエフスキーは、自分自身の父への無意識の殺人願望をイワンに担わせている。
イワンのそそのかしでスメルジャコフがフョードルを殺している。ドストエフスキーはスメルジャコフには自身の癲癇の持病を背負わせている。イワンの願望をスメルジャコフが果たしたことになる。この二人(イワンとスメルジャコフ)は分身(鏡)と位置付けて良いと思う。
父殺しや遺産相続において、最も罪深いのは自分であると気づいたときに、イワンは幻覚症状を起こし気が狂っていく。
シベリア流刑を終えて本格的に作家に復帰したドストエフスキーは獄中でロシア正教を深く信仰し、キリスト教的人道主義に変わり、ロシアの大地に回帰する土壌主義を唱える。まさに精神的な復活である。
ここは、物語においては、敬虔な日々を送る修道僧で心優しく誰からも愛される三男アリョーシャに投影されている。
尊敬したゾシマ長老の腐敗した死体を目のあたりにして神への信仰が揺らぎますがロシアの大地に口づけをして、新たな戦士としての自分を蘇らせる。
教会を出て世俗に入り、現実に直面するもアリョーシャは子供たちに愛され「カラマーゾフ万歳」と喝采を浴びる。この意味は、革命ということでしょう。
ドストエフスキーのこの揺れ動く性質と波乱にとんだ振幅の大きな人生が、三人のカラマーゾフの兄弟に分割されている。
何か大きな事件を起こしそうな未来への予感を残して閉じられた第一の小説(カラマーゾフの兄弟)。
そして次の第二の小説は、ドストエフスキーの死により未完のままとなった。
以上は、ポリフォニーの多声性を、ドストエフスキーというひとりの人間の人生に即して説明してみた。
カーニバル(英語: carnival)とは何か?
カーニバルといえば、謝肉祭というイメージがあります。いっぱい食べて、飲んで、歌って、踊って、楽しんで・・・というような状態。
この部分は、物語のなかで、ドミートリーが、惚れてしまった女性グルーシェンカをえるための派手な大酒宴が繰り広げられる。
モークロエという村で、雑多な出自の人間が集まり、どんちゃん騒ぎをする。
普段、存在する社会的な上下関係や秩序はこのときばかりはありません。
ヒエラルキーなどは存在しないのです、貴族も平民も、金持ちも貧乏も、目上も目下もありません。誰もが主人公。だから日常の主客が転倒する。
無分別の凄まじい生命のエネルギーを孕んでいる。
文学上のカーニバルの意味は、この外面的なお祭り騒ぎと同時に起こる内面的な情動の躍動感もあるのでしょう。
そこでは身も心も開放的となる。だからこそ人間の本心が透ける、あるいは虚実が露わになる場かもしれない。
奔放な女性とされていたグルーシェンカが、このカーニバルのなかで、実は初恋の傷が理由で性悪な女として生きてきたが、いま、心の底から愛しているのはドミートリーだと告白し絶頂となる。情熱的な場面です。
カーニバルが人間の本心を気づかせてくれたことになる
グルーシェンカを父フョードルと競い合っていたと考えていたドミートリーはグルーシェンカの愛を得て、もう死んでもいいという思いになる。
カーニバルが至福の瞬間をもたらせてくれた。ここでドミートリーは父フョードルの殺人容疑で警察に逮捕される。
後の裁判の風景。弁護側と判事側の闘い。証人たちの喚問。農民が多くを占める一二人の陪審員の感情、ここでもそれぞれの人間の思いがポリフォニーとして重なり、カーニバルとして臨場感が高まっていく見せ場となっている。
いよいよ最終の裁定。そのときグルーシェンカは何を語り、カテリーナは何を語ったか。驚くべき結末を迎える。
ドミートリーへの真実の愛に目覚めたグルーシェンカは、フョードル殺人の遠因は自分にあるとドミートリーとともに罪を分かち合おうとし、どこまでも共に生きることを誓う。性悪な女は、痛みを分かち合う愛を捧げる女性に変わった。
対称的に、モスクワの貴族の出で、かつてドミートリーに助けられたことで、生涯を誓ったはずの美しいカテリーナは、自尊心が傷つけられ、裁判において決定的にドミートリーに不利な証言をして有罪を確定させる。高貴な女性は、自己利益だけの傲慢な女に変わった。
そのもっとも大きな理由は、カテリーナが、イワンを愛したからこそ、イワンを無罪にする必要があった。
イワンはドミートリーからカテリーナを奪ったことになる。ドミートリーが犯人になれば遺産の配分も多くなる。
愛も金も手に入れるために、スメルジャコフをそそのかしイワンは父フョードルを殺したのだった。
無意識下のイワンの心に潜んでいた悪が露わになる。
良い女カテリーナ、悪い女グルーシェンカという見えかたが、物語のなかで万華鏡のように違う模様に揺らめき始め、最後は逆になってしまう。
知性派だったイワンは、実は心の奥底に悪魔が棲んでいた。
ここまで確認できた三人の兄弟の心を追いかける楽しみも、その他の人々の心模様もまたポリフォニー構造の醍醐味である。
しかし生身の人間を考えた場合に、決してありえない光景ではない。 人間とは、このような生き物だし、人生もまた変節の産物かもしれない。
そして父フョードルの殺人の真犯人は、スメルジャコフの自殺で明かされることなく状況証拠でドミートリーと裁定され冤罪のなかでシベリア送りとなる。
イワンの思いが憑依したスメルジャコフの復讐は、カラマーゾフの一家を崩壊させた。企んだのがイワンであり、実行したのがスメルジャコフなのである。
私生児ゆえ遺産相続の権利はスメルジャコフにはない。この復讐心と絶望が動機なのか。その罪に苛まれたイワンは発狂状態になる。
実際には、ドストエフスキーの父親(ミハイル・ドストエフスキー)は、作者が一八歳のときに農奴によって殺害される。農奴(ロシア語でスメルド)たちの憎しみと行動(殺人)は、自分自身の願望だったのではないかと後にドストエフスキーは振り返っている。
三人の息子の個性の集合体がドストエフスキーその人であり、農奴たちに殺されたと噂されたる実の父親(ミハイル・ドストエフスキー)を投影したのが物語上の父親フョードルである。
多面的に多層的にポリフォニーとカーニバルで成り立っており、人々は悲喜劇を生きている。その基底に、ロシアの大地に育まれた血があると、ドストエフスキーは、言っているようだ。
この大地とは、古層としての土着的な宗教であり習俗であり文化なのだろう。 その上にロシア正教が融合しており、今、それが崩れていき、金の支配に変わろうとしている。
対する近代化。科学であり唯物的であり、人間の理性が神に勝ると捉える。結果、無神論となる。
強欲な資本主義、個人がバラバラになる自由主義。その先には、破壊の機運が高まってくる。そして革命により社会主義の国家が建設されようとしている。
近代化のなかで神を否定し、金だけを崇拝するロシアと、それを止めようとする運動。ロシアの行く末を憂いている、その作家がドストエフスキーなのである。
それは個人主義を助長させるプロテスタンティズムや、組織や権威というカトリシズムではない。
個と大地が一体となる大きな調和として、個の存在が、大地を成しており、その大地ゆえに個があるというロシアの考え方が揺らいでいる。
私は個人的にはドストエフスキーの作品は、日本人には親近感を感じるのではないかと思う。
人間中心主義の西欧におけるキリスト教観とは異なり、東方キリスト教には、一種の汎神論のような、すべての生なる物が神を称えるという調和があるとされる。
日本人もまた、人間と大地が繋がり、融合している感覚がある。農耕の民族は狩猟の民族とは根本的に異なるのだと思う。
日本人は、本来、自己主張の少ない寡黙さがあったと感じる。寡黙は自問自答の時間でもある。祈りであり、無私の境地である。そして収穫を祝うお祭りの場がある、それは神事である。
日本の小説は、内面のナルシズムの方へ求心力が働いていくが、ロシアの、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』は、たくさんの声を巻き込み、エネルギーを漲(みなぎ)らせながらながら、遠心力を働かせながら大きくなり、その核を揺さぶり、地響きがするように社会を変えようとしている。
その前提に立って読むと、どこか深いところから情念が湧きあがってくる。
ポリフォニーという多声性とカーニバルと言う祝祭性は、これこそまさに人間ドラマであり人間賛歌だと思うのです。