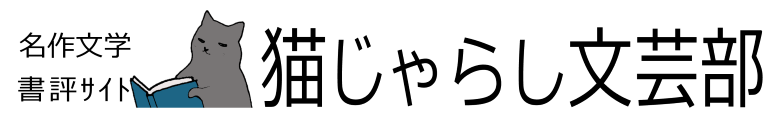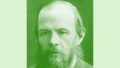最後に感想です
その後のハイルナーの行方は詳しくは描かれていません。ハンスと同じように作者のヘッセは、マウルブロン神学校を半年で脱走します。精神を病むヘッセですが、“神による救い”などないと考えています。
ガンガンと頭痛が止まないなかで、助けを求めるヘッセは、ついにピストル自殺未遂を起こして神経科病院に入院します。まさに圧し潰される状況です。
物語では、父親しかいない設定ですが、実際にはヘッセにとって母親の愛情が救いになりました。
ギムナジウム(中等教育機関)に入学するも、一年足らずで退学。書店に勤めるも3日で脱走。その後、時計工場に勤め、塔の時計の歯車を磨く。再び書店の見習いとなり詩作を始め発表の機会をうかがい、22歳のときに最初の詩集『ロマン的な歌』(1899年)を自費出版します。
さらに分裂した内面を逆手に、架空の友人(ヘルマン・ラウシャー)を設定し、その友人の遺稿を編集するという形で『ヘルマン・ラウシャーの遺稿の文と詩』(1901年)を発表。24歳で成功をおさめ、ヘルマン・ヘッセとして知られることになります。
車輪の下と、潰されない意志
品行方正な優等生だったハンスの変わりようを見て、校長がハンスに放つ言葉。
へたばらないようにするんだよ、
さもないと車輪の下に圧しつぶされてしまうよ
学業が落ちていくハンスをたしなめる場面です。
「勉強を真面目に怠らないようにしないと脱落するよ」という意味なのでしょう。「車輪の下に圧しつぶされる」とは「学校に抗う者は、潰されてしまう」。つまりは堕落する。極論すれば、(つぶされて)死んでしまうということなのでしょうか。
その説教には、暗に問題児のハイルナーなんかと付き合うなと言っている訳です。案の定、校長は続けます。
「おまえはハイルナーとずいぶん付き合っているようだね」と尋ね、校長は「ハイルナーを好きではない」とはっきり言います。「頭は良いが勉強をしない、不平不満の多い、落ち着きのない子だ」とつまり不適合者だと言うのです。ひどいですよね。
これに対して、ハンスは「親友を見捨てることはできない、そんなことをしたら卑怯者になる」と答えます。
ここまで来ると、「車輪の下」とは、学校の教育方針であり、「圧しつぶされてしまう」とは、抗い駄目になるということです。この言葉を、権威があり、権力もある、マウルブロン神学校の校長が使うのです。
親友を見捨て、学校の言うとおりに学業に励むことが、車輪の下に圧し潰されないことなのか。
それでも、ハイルナーはハンスの散策に付き合う。校長はハイルナーを叱責し数時間、監禁をする。その後、ハイルナーは脱走するが見つかる。結局、ハイルナーは謝罪もなく 恭順の意を示すこともなく、放校処分を受ける。そして消息を絶った。
ハイルナーは早々に、欺瞞に気づき学校を去ったのです。
ハンスは、校長や、父親、教授たちによって力づくで、彼らの考える正道に戻そうとされる。その結果、ハンスは、周囲からの抑圧につぶされてしまいます。医者はハンスを神経衰弱と診断する。そして学校は静養のために休学とするが、校長はハンスが二度と戻ってこないことを知っていた。
私はエリートに欺瞞を感じてしまう。彼らにあるのは、権力と金と虚栄心だけではないのか。高潔さなど微塵も感じない。
幼いころの原風景の記憶でも良いし、信仰でも、哲学でも良い。悩むこと、その先に生きる意味をみつけ、これが生きることであり、そのために自分はあるといえる何かを見いだせることは素晴らしいことである。
物語の少年たちは、3つに分かれている。
ひとつは優秀で学校を卒業するであろう選民意識の高いエリートたち、将来を約束されている人々。もうひとつは故郷に根付いている普通の人々、さまざまな仕事を営み、社会を支えてもいる。最後は、どちらにも適合できな少数。
ハンスとハイルナーを掛け合わせた存在がヘッセその人である。ヘッセのなかに二人の性質が棲んでいる。
『車輪の下』では、二人ともに学校を去るが、ヘッセは、悩み苦しむハンスを事故死(あるいは自裁)させ、自己を信じるハイルナーを未来へ旅立たせた。
「詩人になるか、でなければ、何にもなりたくない」そう思い続けた少年の日から、ヘッセは、学校もどんな仕事もうまくいかない人生でした。
「車輪」とは何か。物語では、それは学校(校長やその構造)です。国家やイデオロギーという場合もあるでしょう。ヘッセにとって、それは個人の精神を抑圧するものでした。
ヘッセは、学校からは嘘をつくことしか学んでいないとし、信仰は大切にしているが、教会の説教はおしつけと感じている。
作家となり成功したヘッセを待っていたものは、戦争という運命でした。その時代に中年となったヘッセはどう生きたのか。
第一次世界大戦の大量の殺戮のなかで、ヘッセの作風は大きく変わります。自身の内面の危機のなかで、宗教や社会や国家に向き合います。その深い精神世界を描いた『デミアン』(1919年)。その後、南スイスに単身で移住し、以降の作品(『シッダールタ』『荒野のおおかみ』など)では、近代への文明批判や個の魂の解放を目指していきます。
第二次世界大戦下では平和を唱えるヘッセは、詩の形をとおして「ファシズム(ヒトラー/ドイツ)にもコミュニズム(スターリン/ソビエト)にも下るくらいなら死を選ぶ」と発表しています。
そこには民衆を巻き込んだ狂信的なイデオロギーを否定する姿がありました。共通するのは危険な権力や集団主義でした。
ヘッセは、戦争という、もうひとつの大きな車輪の下に、圧しつぶされることなく、自らの魂に従い、平和を思い続けた人でした。その後、『ガラス玉演技』を最後に、一線を退きます。
晩年は、ロマン・ロランやトーマス・マンのような著名な作家と書簡を往還します。さらに読者から寄せられた手紙を読み続けるとことを日課とし、読者に返信を出し勇気づけました。ヘッセはひとりひとりに語りかけることをあきらめませんでした。
ドイツを代表する文豪であり、詩人の魂を持つノーベル文学賞の作家というだけでなく、ひとりの人間の生きた半生として、その青春の悩みを描いた牧歌的な時代から、以降の戦争の悲惨な時代を生きぬいた高潔な文学者として、宗教、哲学、歴史、政治を紐解きながら自己の内面と世界の関係を問い続けました。
個性的な人間にとって、この世は生きにくいものです。
しかし、そうした人間にとって、人生とはより美しくもあるのです。
ヘッセの言葉です。
思春期に、ハンスとハイルナーの精神に触れた多くの日本の少年たち。あのときに感じた不満、危うさや脆さ、そして反抗心。
現在のあなたはいかがでしょうか。車輪の下につぶされてはいませんか。つまらない大人になるために、大切なものを失ってしまってはいませんか。青春の季節を越えて、過去を回想する。
その感受性を慈しむために、この作品を再読してみるのもいいですね。