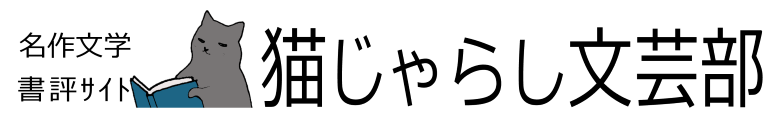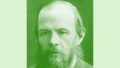「詩人になるか、でなければ、何にもなりたくない」そう思いつめた少年の日。牧師になることが当然とされた将来。重くのしかかる周囲の期待。父親、親戚、故郷の人々、校長や先生たち。これは、南ドイツの自然に育まれ天賦の詩才にあふれたヘッセの自叙伝的な青春の苦悩の物語である。豊かな感受性と反抗心、大人へ旅立つ不安な思いに満ちた思春期を回想する。ハンスとハイルナー、掛けあわされた二人の内面こそがヘルマン・ヘッセその人だったのだろう。
動画もあります!こちらからどうぞ↓
あらすじと解説
自分を育んでくれた原風景を忘れない。
「はじめに神話があった」で始まる、前作の『郷愁―ペーター・カーメンチント』(1904年)。
自然は雄大で美しく、その細部が詩的に描かれている。山と湖と太陽、何よりも雲を愛する主人公カーメンチントもまたヘッセ自身である。
この作品を踏まえ、『車輪の下』(1906年)を読むと、確かに詰め込み教育や、厳格な規則の寮生活は息苦しい。ここで心身のバランスを崩していくハンスだが、もともとヘッセ自身が均質な模範人間を製造する学校という機能に適合できない人間であり、詩を愛する少年だったことが前提だとわかる。
学校の批判や皮肉にみちた描写に対して、釣りや泳ぎを楽しみ、故郷の人々を慈しむハンス・ギーベンラートの自然児としての性質。先生は、優秀で選ばれた人間という優越感をおしつけ、生徒たちの夢や友情や自発性を奪っていく。
親子の絆はもちろん基本ではあるが、情操は自然の体験や周囲の共同体のなかで育まれるものが大きいのではないのか。
ハンスは州試験を受けるために、ラテン語やギリシャ語を猛勉強する。故郷の人々は-敬虔な靴屋の親方のフライクおじさんも、信仰心の薄い町の牧師も、幼馴染の友だちもそれぞれの言葉でハンスを応援する。
一緒に遊んだアウグストは、すでに学校をやめて機械工の見習になっていた。
目指すは超難関、マウルブロン神学校。試験の日がやって来る。ラテン語はやさしかったがギリシャ語はむずかしかった。その後の口頭試問もうまくいったかどうか・・・翌日の数学と宗教は大丈夫だった。それでも落ちたのだろうと思った。
ハンスは故郷に帰ると、楽しみにしていた川に泳ぎに行く。ほっとして家路につくまでにたくさんの人々の記憶に遊んだ。
思いもかけず合格の知らせが来た。驚いたことに二番という成績だった。するとハンスは一番でなかったことを残念に思った。9月の入学まで、一足早い休みとなり、好きな釣りを楽しむことができたが、それも束の間、良いスタートを切れるようにと翌日からまた猛勉強を強いられた。
合格者は各地方から優秀な生徒が集まり総勢で40名。入学式では校長が祝辞をする。同級生は寄宿舎に入りいくつかの部屋に割り当てられる。生徒たちは品行方正である限り、卒業すれば、牧師となり、一生涯、国家から生活も職も保障される。名誉と安定が約束されているのだ。
制度に従順な「学業」か、自身の抱く「夢」かの間で揺れる。ここがミスマッチとなった場合。思春期、そして青年へと羽ばたくこの時期ほど、デリケートな季節はないだろう。
同じ部屋に、詩才があり、文学好きなヘルマン・ハイルナーという生徒がいた。まるで感受性をむきだしにしたような少年。やがて問題を起こし始める。宿題をやらないし、授業をさぼる。
しかし心の底には、深いものを持っていて、詩人になることを目指し、すでに自分の道を歩み始めているようだった。
ハンスは勤勉で、真面目で模範的。ハイルナーは天才で、自由で奔放。
森を散策しながら詩を作るハイルナーにハンスは興味も持ち、いったいどういう人間なのか・・・。
あの男は、
自分の魂を詩のなかに映し、空想から独自の架空の世界を創りあげる、風変わりな神秘的な技を心得ている。
独自の考えや言葉でいきいきと自由な生活をし、ふしぎな悩みに苦しみ、周囲のものをすべて軽蔑しているように見える。
ハイルナーはどこか孤独で甘えん坊だった。だから自分の心を打ち明けることができる友が必要だった。それがハンスであり、彼にだけは心を開いた。
ハンスは、自然を愛した自分から、勉強しかない自分に変わったこと。そして大人たちの期待を背負っているだけの自分に疑問を持ち始め、頭痛やめまいに苦しめられ体調を崩し始める。
ヘッセのなかに、ハンスとハイルナー、ふたつの性質が同居している状態です。
ハイルナーは、ますます悪化していった。あるとき、同じ部屋のルチウスという少年と喧嘩になり、校長の部屋に逃げこむところを蹴り上げて、その現場を校長に目撃され謹慎の処分を受ける。
このときハイルナーが信頼していたハンスは、この騒動に関わらず無関心を装った。それはハイルナーにとって裏切りの行為であり、ハンスを下劣な卑怯者と考えた。
ハンスとハイルナー、二人の仲はひび割れた。
このころ、同級生の一人が事故で、池に落ちて溺死した。生徒たちは“死”というものを目の当たりにした。この不幸な出来事は、ハンスを少年から大人へと導いていった。
ハンスはなぜかハイルナーへの罪の意識が深まった。
謹慎によって、孤独を深めるハイルナーに、ハンスは自分の卑怯さを詫びた。このことで、ハンスは前よりもやさしく、温かみがあり、熱中しやすくなった。ハイルナーはいちだんと、たくましく、男らしくなっていった。
二人の友情は、元に戻った。
ハンスは解放され、ハイルナーは飛び立った
ハンスは、最初、ハイルナーと自分は正反対の性格だと考えていた。しかし、次第にハイルナーに惹かれていく。詩を愛するハイルナーは、学校生活の型にはまっていない。まさに型破りなのである。感情の起伏も激しく問題児だが、そのことを自分では、気にもせず何とも思っていない。
ハイルナーの天才的な性向は、教師たちから気味悪がられる。
天才と教師の間には、埋めがたい深い溝がある。天才的な人間が学校で自分をむきだしにすると、教授たちは危険なものとしてしまう。
校長は、最初はハンスもハイルナーも可愛がったが、やがてハイルナーを問題児として排除しはじめ、ハンスをハイルナーから引き離そうとする。ついに校長は、婉曲的ではあるが、ハンスにハイルナーと付き合うことを禁じる。
文中に、
教師の任務は、規格外の人物を育成することではなく、ラテン語や数学のできる実直な小市民をつくりあげることにほかならない。だが、より大きな被害をこうむるのはどちらだろう。教師が生徒から受けるのか、それともその逆なのか。両方のうち、どちらがより暴君であり、加害者なのだろう。相手の魂と生活をめちゃめちゃにし、よごしてしまうのはどちらだろう。(中略)
とある。
作者のヘッセは明らかに、生徒たちの個性や可能性を尊重しており、学校がそれを奪うことを否定している。
ハンスは、喧嘩の一件で、一度はハイルナーを裏切るが、そのことで自分を恥じ、ハイルナーに謝罪し、再び友人として固い絆で繋がっていた。
謹慎が解かれても、ハイルナーは従順になることはなかった。
ハンスは、ハイルナーの友情と校長の方針との板挟みになり、悩みはじめる。しかしハイルナーを守ることを優先する。成績は上位から下位へさがっていくが、気にしなくなった。
ハンスは友を裏切らなかった。しかし校長はハンスを見捨てる。その後、ハイルナーは学校を脱走する。
自らの意志に生きることを決心したのがハイルナーであり、心身のバランスを崩してしまったのがハンスである。
故郷に戻ったハンスは、天気のいい日に森のなかで横たわっていると、遠い昔の自然と遊んだ記憶がよみがえってきて、傷ついた魂をすこしだけ明るくした。
最初、父親はおおいに落胆するが、やがてハンスの精神の不安定さを心配する。
思いつめていくハンスは、自分の存在を否定するようになり、苦悩と孤独のなかでピストルを手に入れるとか、森のどこかで縄をかけるとか、自殺の衝動にかられる。
秋も深まるころ、ハンスの気持ちも落ち着き自殺を考えることはなくなりかわりにメランコリー(憂鬱症)になっていった。収穫の時期になり、靴屋のフライクおじさんは、気分転換にハンスを果樹園での林檎(果汁)絞りに誘う。
そこにはフライクの姪のエンマという女性も別の地方(ハイルブロン)から手伝いに来ていた。
娘は18か19で陽気でいい体つきをしていた。俗っぽく底抜けに快活だった。ハンスはエンマに主導されてはじめて女性とキスをする。ハンスの思いは募っていく。それは遊びなれた女性に振り回されただけだったが、ハンスは淡い恋心の体験もした。
回復していくハンスは職工になることを決断する。もうすぐ一人前になるんだと誇らしく話す幼馴染のアウグストや工場の仲間たちに励まされる。はじめは不慣れな機械工の仕事だったが、次第に体を動かすことに楽しさを感じる。以前のように気の毒な職人風情という意識はハンスにはもう無かった。小路を歩くとき、何ヵ月ぶりかで日曜日の楽しみも味わった。
仕事休みの日に、ハンスはアウグストからの祝いとして、仲間たちと一緒の酒宴で、御馳走になり気をゆるめ痛飲する。
酔いのなか、ハンスは幼いころの記憶が蘇る。生家の路地に通じる2つの家並み。ひとつは金持ちが多く、もうひとつは貧乏が多い。貧乏人の通りには変わった暮らしをする人々が住んでいて、なぜかハンスはその人たちの記憶を懐かしんだ。
それはいつか学校時代の記憶と混ざりあってしまう、そんな幻想にも似た時間が巡った。ハンスは前後不覚になるほど泥酔し、川に落ちて事故死(自裁かもしれない)してしまう。それはあっけない最後だった。
きれいな顔は、まどろんでいるようで、こころもち開いた口は満足そうで、楽しげにさえ見える、と描写される。ハンスは、やっと苦しみや悩みから解放されたようである。