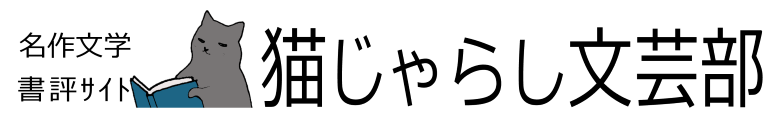幼少の記憶を友人は私に話す。それは時間が経つのも忘れるほど蝶に夢中になったあの頃の熱情。憧れが、抑えきれない欲望となり、衝動的に盗みをはたらく。我に返るがそれは壊れて修復不能になり、大きな心の傷となる。最高の美しさが、脆く、粉々に消えた。自分の手でそうした。これほど辛いことはなかった。そして自分を罰し全てを葬り去ったひと夏の夜。話を聞く私はどう思ったのか。
動画もあります!こちらからどうぞ↓
あらすじと解説
この作品は、中学校の国語教材として長く採用され、試験問題の対策的に紹介されていますが、ひとつの短編小説としても味わい深いのです。
夜の深い暗闇の向こうから、子どものころの性質が蘇ってきます。それは今も変わっていないかもしれません。きっと一人の人間のなかにある複雑な両面性だと思います。
作品は、現在から過去を回想しています。現在は、「私」と、来訪者の二人だけです。思い出に登場するのは、少年、エーミール、少年の母親です。この来訪者が、現在の視点では、「客」、「友人」、「彼」と呼称され、思い出の視点では、主人公の「ぼく」となります。つまり「客」、「友人」、「彼」、「ぼく」は同じ人物ということになります。
・・・ということで解説してみます。
宝物と宝石、蝶への思いの違い
「客(=ぼく、彼、友人)」は、「私」の書斎でくつろいでおり、息子がおやすみなさいと挨拶したのをきっかけに、お互いの子どものころに話が及ぶ。
「私」は蝶の採集をまた始めたんだよと告げ、採集箱のなかの珍しい蝶を見せると、「友人(=客、ぼく、彼)」は、何かを思い起こしたのか「もう結構!」と蓋を閉じる。
蝶ほど幼少を思い出させるものはないと言い、「彼(=ぼく、友人、客)」は少年のころを回想し始めます。客であり、友人であり、彼である男性(すべて同一人物)は、「ぼく」に変わります。
8歳か9歳くらいから始めた蝶採集。自然の中で蝶を捕まえる楽しさ。10歳のころには我を忘れるほど夢中になり、すっかりとりこになった、はじめてのキアゲハにしのび寄る瞬間、それは子どもだけが感じることができる「むさぼるような恍惚感」であり、採集した蝶は、古いつぶれた段ボールの箱にワインの栓のコルクを台にして刺した。
この蝶への熱情は、周りのみんなが止(や)めさせなければと思うほどだった。
「ぼく」にとって、それは「宝物」だった
まさに無我夢中、我を忘れて心を奪われている状況です。
あるとき希少種のコムラサキを採集し、うれしさのあまり隣に住む先生の息子のエーミールだけには見せたかった、
エーミールはどこからみても完璧でいやな奴。わずかばかりのコレクションしか持っていないが、標本は美しい。それは「宝石」のようだと表現される。さらに高度な翅 (はね) をひろげる技術(展翅技術)を持っていた。
まだ10歳です。几帳面で忍耐強い真面目な子どもですよね。
「ぼく」の方は、蝶の採集に夢中で、標本作りには気持ちが及んでいない。標本の道具や技法も含めて完璧なエーミールは、「ぼく」から見れば、模範少年。それはガラスケースに並ぶ美しい観賞用の展示物のようです。
ぼく(客)から見れば、それは宝物ではありません。
「ぼく」はこのエーミールを妬(ねた)みと感嘆(かんたん)の思いで憎んでいた、とあります。つまり「ぼく」はエーミールをたいした奴だと認めながらも、その完璧さが嫌いなのです。悪徳とすらされています。子どもらしく無いと思っているのでしょう。
「宝物」と「宝石」の違いは、実感として分かります。
少年にとって、宝物と宝石は比べる対象ではありません。希少種はさらに唯一無二の「宝物」なのです。
だからコムラサキを採集したときには、エーミールだけには見せたかったのです宝物を自慢したいし、その価値を鑑定してもらいたいのです。「ぼく」がエーミールに対して、味わうことのできる優越感もあるのかもしれません。
因みに、日本では蝶と蛾は別の捉え方をします。蝶は奇麗で、蛾はキモイとか。でもドイツでは蝶と蛾の区別がないらしいのです。
欲望の果てに、こなごなになった挫折感
エーミールは、ぼくのコムラサキに(20ペニヒ≒2,000円)の価値を認めるが、その標本状態に、あら探しをはじめる。展翅の仕方が悪いとか、右の触角が曲がっているとか、脚が二本欠けているとか。
つまり完璧の反対、欠陥がいっぱいあるといっているのですね。
このことで「ぼく」は傷つけられ、二度とエーミールに蝶の標本はみせなくなった。
それから2年後(12歳のころ)、エーミールがクジャクヤママユを蛹(さなぎ)から羽化(うか)させたという噂が広まる。少年の「ぼく」たちにとっては、このことは何にも増して世界一の大ニュースです。
「このとび色の蛾が木の幹か岩にとまっているとき、小鳥やそのほかの敵がそれを攻撃しようとすると、その蛾はたたんでいた黒っぽい前翅を引き上げて、美しい後翅(こうし)をあらわにする。その後翅の明るい眼状紋がとても奇妙な、思いもかけない様子に見えるので、小鳥はびっくりしてその蛾をそのままにして 行ってしまう。
天敵の攻撃をそらすために大きな目の模様があると伝えられれば、そりゃ興奮しますよね。少年は舞い上がってしまいます。
「ぼく」の熱情は最高潮です。それはお金なんかでは代えられない。百万マルク(≒1億円)よりも価値があり、冷静さなど全くなくなっています。一目見たさに、さっそく隣の家を訪れます。
エーミールの部屋の鍵は開いていました。こっそり中に入り、クジャクヤママユを見る。しかし展翅板に乗せられていて、肝心の眼の紋様(眼状紋の部分)がテープで覆われて見えません。
眼状紋をどうしても見てみたい。
つい、留め針を抜き、テープをはがして見る。4つの大きな不思議な眼がぼくをじっと見ている。どうしても自分のものにしたくなり、ついに盗んでしまう。そのとき大きな満足感を味わう。
階段を下りるところで、誰か上がってくる人の気配を感じ、そのとき良心が目覚め自分がなんて下劣な奴だと思った。右手に隠していたものを本能的にポケットにしまいこむ。うまく下に降りたが自責の念で、メイド(上がってきた人)に気づかれないように部屋に戻って机の上に返すと、
クジャクヤママユが壊れていた
前翅が一枚と触角が一本なくなっていた。ちぎれた羽を引き出すとボロボロになっていた。
罪の意識よりも、自分が壊してしまった珍しい蛾を見ている方がつらかった。
これは盗みの気持ちよりも、最高のクジャクヤママユを、自らの行為でつぶしてしまった、その無残な姿を見ていることの辛さです。こころがしめつけられるほどの苦しみでしょう。
家に帰り勇気をだして母親にうちあける。母親は「自分でエーミールにきちんと伝え、謝罪し、持っているもののなかから弁償をさせてもらう」ことをお願いするようにと、「ぼく」は諭される。
エーミールのところへいくと、なんとかクジャクヤママユを元通りに修理しようとしていたが不可能のようだった。それをやったのは「ぼく」だと言い、説明しようとした。
するとエーミールはどなりつけるかわりに、歯笛を吹いて、「ぼく」をじっと見て、それから「そう、そう、きみって、そういう人なの?」と言った。
「ぼく」は、おもちゃを全部あげる、コレクションを全部あげると言うと「どうもありがとう。きみのコレクションならもう知っているよ。それにきみが蝶や蛾をどんなふうに扱うか今日またよく見せてもらったしね」と言われる。
この瞬間、「ぼく」はもう少しであいつの喉笛に飛びかかりそうになった。
歯笛をふかれて、喉元を目がけて、つまり首絞めにいくって完全にキレようとしていますよね。こうしてエーミールが正義であり秩序であり、「ぼく」は永遠に悪党であり続けることが決定します。
「ぼく」は一度だめにしてしまったことは二度ともと通りにすることはできないと、はじめて悟ります。
「ぼく」は床に就く前に、食堂においていた大きな段ボールをベッドの上に置き、暗がりのなかで蓋を開けて次から次に蝶や蛾をとりだし、それを指で粉みじんに押しつぶしてしまった。
熱情⇒憧れ⇒欲望⇒衝動⇒窃盗⇒後悔⇒自罰⇒決別のような流れで、「ぼく」の心の変化が描かれます。